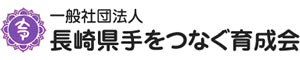育成会について
理事長挨拶
令和7年度 社会福祉法人長崎市手をつなぐ育成会 定期総会
本日は長崎市手をつなぐ育成会の定期総会です。
今年の開催場所は、この総合福祉センターとなり、皆様には戸惑わせてしまったのではないかと心配しておりますが、このように一堂に会しての会が開かれることとなり、喜ばしいことだと思っています。感謝申し上げます。
さて、僭越ながらご報告をいたします。この5月28日に東京に出向き叙勲(旭日単光章)をうけてまいりました。皆様からのご支援のお陰と心より感謝申し上げます。
大変名誉なことだとは思っておりますが、あまりにも自分の身に余ることでしたので、自分に起こったこととは思えませんでした。ただ、叙勲の内定が決まりました時、初代の田川理事長をはじめとする歴代の理事長さんや、法人準備委員会で法人化への道をともに歩んだ多くの先輩たちのことを思い出しました。当時、知的障害のある人たちが安心して通える施設を自分たちで作ろう、知的障害のある方たちが普通に暮らせるふるさと長崎にしようと勢い込んでいたように覚えています。そういう中で、役員さんばかりでなく多くの先輩たちが静かに私たちを支え、応援してくださっていたなと皆さんのお顔を思い出します。そういう多くの皆様と共に今回の叙勲はいただいたのだと思うことにしました。皆さんの右代表でいただいたと思うと、なんとなく腑に落ちるというか、穏やかな気持ちでお受けすることができました。
私も、この仕事を始めて35年となりますが、最初は一母親として息子の為だけに活動をしていたように思います。しかし、ある時、山内先生から「福祉を仕事として取り組むように」と言われて、自分自身の方向性を切り替えていくのはシビアなことできつかったことを思い出します。
今は多くの皆さんが私の周りにはいてくださって、私を支えてくださっています。多くの皆さんのお力で現在の私も恙なく仕事ができているようです。ここに深く感謝の気持ちを皆様にお伝えしたいと思います。本当にありがとうございました。
さて、昨年の活動を振り返って皆様にお伝えしたいことは沢山ありますが、一つ取り上げると、障害のある人対象の模擬選挙のことだと思います。一昨年の長崎市の市長懇談会の席で、自閉症協会との共同で「障害のある人の投票場の環境」について発言をしました。長崎新聞に自閉症協会のお母さんから投稿があり、障害のある息子さんを投票に連れて行っても環境も人の体制も整っていないという内容で、ちょうど「手をつなぐ」に知的障害の方たちの投票についての先進地の記事が掲載されており、共同して要望することになりました。これまで、ハートセンターの期日前投票で障害のある方たちも投票に行きやすくなった事実、しかし、コロナを挟んで色々な事情でハートセンターでの期日前投票が中止になったり、開所日が半減したりしました。期日前投票のことも含めて要望したのでしたが、長崎市の選挙管理委員会は障害のある人たちのことをもっと知ることが大事だということで模擬選挙に取り組んでくださいました。今年で模擬選挙としては3回目となります。今年の模擬選挙は当法人の夢工房みどりで行われ、事業所を投票場にする初めての取り組みとなりました。その時に、選挙管理委員会の方や障害福祉課の方たちが、利用者の方へ丁寧に情報提供し、お気持ちを引き出そうとする夢工房みどりの支援の実践にカルチャーショックを受けておられたようでした。感動したと言われてました。障害のあることを理解してもらい、何がその方たちに必要なのか、選挙管理委員会の方は多くを学んでくださったようです。
また、選挙に関しては親さんからもうちの子は何もわからないからとか理解できないとかいわれますが、本当にそうなのでしょうか。何もわからない人ということで情報も知る環境も与えられていなかったのではないか。立正大学の教授でごきょうだいでもある打浪文子先生の言葉で知的障害者を「知ることから遠ざけられてきた人」という表現で挙げておられます。知的障害のある人たちはわからないことをわからないと自分から伝え、その後分かりやすい言葉や表現でちゃんとした情報を得ることができてきたのでしょうか。他の障害の方たちへは、点字もあり手話もあり、要約筆記もあり、ICTを使った様々な合理的配慮が実現する世の中になりました。そういう意味でも、選挙だけではなく、知的障害の方たちのための分かりやすい情報提供の仕方をあらためて考えてみなくてはいけないようです。そのことが知的障害の方たちの人権を守ることにつながっていくのではないかと考えるのです。
今日の総会は、会員定例会拡大版ということで、知的障害の方たちの気持ちに寄り添える意思決定支援について、一緒に考えてみたいと思います。
難しいテーマですが、最後までよろしくお願いいたします。
令和7年7月5日
社会福祉法人 長崎市手をつなぐ育成会
理事長 谷 美絵
役員紹介
第17期役員
任期:令和7年6月28日から選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
| 理事6名 |
|
|---|---|
| 監事2名 |
|
評議員名簿
第15期評議員名簿
任期:令和7年6月28日から選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
| 評議員7名 |
|
|---|
沿革
育成会とは
昭和27年、東京の知的障害児を持つ3人の母親たちの小さな運動が育成会運動の第一歩です。
各地でそれぞれの育成会が組織され、その連合体が全日本手をつなぐ育成会です。
わが長崎市手をつなぐ育成会の第一歩も同じように、親たちの願いにより始まり、以来、手をつないだ親たちの輪も大きくなり、その歩みも確かなものになってきています。
一人ひとりの本人や親の願いが、育成会を動かす大きな原動力なのです。
| 昭和29年 | 浦上学園育成会「手をつなぐ親の会」結成 |
|---|---|
| 昭和34年 | 長崎県手をつなぐ親の会が結成し前身の長崎支部誕生(会員数86名) |
| 昭和39年 | 長崎市精神薄弱者育成会と改名 |
| 昭和43年 | 長崎市心身障害(児)者援護育成会と改名 |
| 昭和53年 | あじさい福祉作業所開所 |
| 平成 6年 | 法人化が認められ、社会福祉法人長崎市心身障害者育成会と改名 |
| 平成 7年 | 通所更生施設「あじさいの家」開所 |
| 平成10年 | 知的障害者ガイドヘルプ事業を市より委託 |
| 平成11年 | 育成会設立40周年記念式典開催 |
| 平成12年 | 社会福祉法人長崎市手をつなぐ育成会と改名(会員数500名) |
| 平成13年 | 通所授産施設「ワークあじさい」開所 |
| 育成会在宅支援5カ年計画スタート | |
| 平成14年 | グループホーム六じぞう、グループホーム京泊開所 |
| 平成15年 | 小規模通所授産施設「さんらいず」開所、みどり作業所開所 |
| 平成16年 | グループホームなめし開所、デイサービスセンターおあしす開所 |
| 平成17年 | グループホームはやま開所、タイムケア事業を市より委託 |
| 平成18年 | 育成会ケアプランセンター(居宅介護支援事業、相談支援事業)開所 育成会ヘルパーステーション事業移行 (居宅介護事業、重度訪問介護事業、行動援護事業、訪問介護事業) 夢工房みどり(就労継続支援事業、自立訓練事業)開所 日中一時支援事業(デイサービス型)「おあしす」事業移行 日中一時支援事業(タイムケア型)「フレンズ」事業移行 NPO法人成年後見センター「ふぇいす」開設 |
| 平成19年 | さんらいず(就労移行支援事業、就労継続支援事業)開所 |
| グループホーム城山台開所 | |
| 第2次育成会地域福祉5カ年計画スタート | |
| 平成20年 | グループホーム女の都開所 |
| ながさき知的障害児者生活サポート協会開設 | |
| 平成21年 | 育成会創立50周年記念式典開催 |
| 平成23年 | あじさいの家、ワークあじさいが新事業体系へ移行 |
| 平成24年 | 陽香里工房(生活介護事業、就労継続支援事業)開所 |
| グループホーム十人町開所 | |
| 第3次育成会地域福祉5カ年計画スタート | |
| いんくる(長崎市障害者相談支援事業)開設 | |
| 平成26年 | ケアホーム三京開所 |
| 平成27年 | グループホーム西北開所 |
| 平成28年 | ケアホームさくら開所 |
| 平成30年 | グループホームライフ西北開所 育成会生活支援センター開所(事務所移転[本部、他7事業所]) 第4次育成会地域福祉5カ年計画スタート |
| 令和元年 | ケアホームさくら短期入所棟開所 育成会創立60周年記念イヤー |
| 令和2年 | ケアホーム陽香里開所 |
| 令和3年 | グループホームはやま移転 |
| 令和4年 | グループホーム六じぞう移転しグループホーム青山に改名 |
| 令和5年 | 長崎市障害者基幹相談支援センター開設 |
組織図
地域福祉五カ年計画
地域福祉五カ年計画 地域福祉五カ年計画概要解説デジタルカタログ
デジタルカタログ育成会職員行動規範
基本的な考え方
- 職員は、利用者の人権を尊重します。
- 職員は、利用者の意思を大切にします。
- 職員は、福祉従事者としての誇りを持ち利用者に良識ある態度で接します。
- 職員は、福祉従事者としての自覚をもち、絶えず学び、研修し、サービス提供の責任を果たします。
- 職員は、利用者とともに運動体である育成会の一員として行動します。
- 職員は、謙虚さを心がけ、人間としての成長を目指します。
- 職員は、地域福祉の担い手として、あらゆる社会資源とのネットワークを創ります。
基本姿勢
- 利用者への明るい笑顔と元気な挨拶を忘れずに支援します。
- 利用者を友好的に迎えいれ、愛情を持って支援します。
- 利用者の安全・安心を第一に考えてすみやかに行動します。
行動規範
- 利用者を「○○さん」と呼びます。
- 利用者へ丁寧な声かけ、言葉づかいをします。
- 利用者への支援を始める時は、まず声かけをします。
- 利用者への虐待は行いません。
- 利用者に対して、無視、命令、威圧的な言動をしません。
- 利用者の行為の嘲笑や興味本位での対応をしません。
- 利用者に承諾なしで所持品の確認をしません。
- 利用者の特性を理解し、わかりやすい説明を心がけます。
- 利用者の個人情報は厳重に管理し、外部に漏らしません。
- 利用者の着替えや排泄に関することなどプライバシーの保護には十分配慮します。
- 利用者に対し「ありがとう」と「ごめんなさい」はしっかりと伝えます。
- 利用者からの苦情に対し誠意を示し速やかに対応します。
- 利用者の安全を守るための危機意識を常に持ち、環境整備を行います。
- 利用者の健康に心掛け、その様子や状態を観察します。
- 利用者が生活に必要なスキルを獲得できるように工夫します。